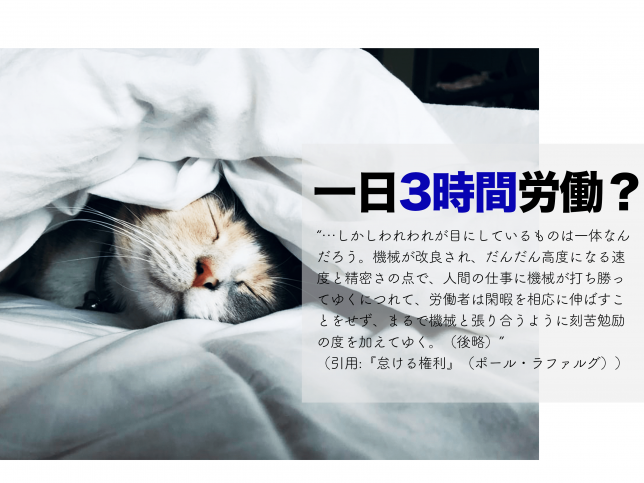怖いのは、今ある環境や一般的な”普通”を疑えなくなる事だと思います。
それは必ずしも、世間を斜めから見るクセをつけようということではなく、物事を鵜呑みにし過ぎてしまうことへの懸念、考えることすら放棄してしまうことへの懸念です。
『怠ける権利』(ポール・ラファルグ)
フランス第三共和政期に書かれた『怠ける権利』(ポール・ラファルグ)を何度か読んでみて、今に繋がっている話が既に140年前からある事に驚きます。引用は今まで一度もしたことは無いと思うけど印象に残った一文があるのです。
“…しかしわれわれが目にしているものは一体なんだろう。機械が改良され、だんだん高度になる速度と精密さの点で、人間の仕事に機械が打ち勝ってゆくにつれて、労働者は閑暇を相応に伸ばすことをせず、まるで機械と張り合うように刻苦勉励の度を加えてゆく。(後略)”(引用:『怠ける権利』(ポール・ラファルグ))
140年後の今にもほぼマッチする
140年後の今にもそのまま一ミリも違わず当てはまる文章ですよね。今から140年後、相当に技術が発展して、今いる誰もが生きていないような未来の世界でも、案外、仕事事情はいまと変わらないかもしれません。そう思うと希望もない。進歩とは幸せと反比例するものなのかとすら、思えてきます。
浮いた時間は手に入らない
技術で”浮いた”時間は決して還元されることはなく、さらなる稼働が求められる、それはアイドルタイム、空いている時間なのだから何しろ動かさなくては無駄になります。効率が悪い。投資されるべき時間。この本を読んで、それを疑ってゆく、そろそろ時期ではないかと感じました。その考え方普段から念頭にあって、この本が初めて感じたことではありませんが。
これだけ距離も時間も飛び越せる技術の中にいれば、1日3時間労働(本書)でも多いくらいかな。でも、そうでもない。時間は概ね足りないことが、残業申請が止まることがない現状からもわかるように思います。自分も例外ですね。
根本原因は[時間]の概念
その根本的な原因は[時間]の概念なのでしょうか。時間は埋めなくてはならないもの。空き時間は無駄、というその考え方がベースにある以上、どんなに技術がハイパーに進化しても生物的な幸せを更新することはできないように見えます。何しろ本来は、人間は時間でできていません。猫が時間とは無縁なように。
生とは時間あたりの総出力量なのか
生きることとは、時間あたりの総出力とか効率性の追求と等しいことなのか。ビジネスのフィールドでのみ生きるスキルとしてのそれが、[生きること]全般にまで、悪いい意味で敷衍してしまっていないかな。ワインも果実も牛肉も森も、そして人も時間をかけてはじめて熟します。生き物なのだから当然なのでしょう。
怠けるということは、不真面目に、適当にやっちゃおうということではなく、そもそもの自然的生物(言語矛盾か)としてのスタンスを、見直そうという姿勢を面白おかしく表現したものです。それくらいの急進性があっても良いと個人的には思います。